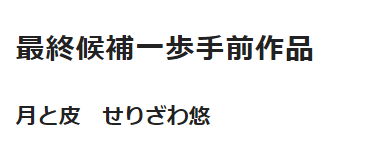ジャンプ・ホラー小説大賞 まさかの最終候補一歩手前だった話。

芹澤です。
時々「せりざわ」だったりします。
少し前に結果が出ていたジャンプホラー小説大賞
当然のことながら私の名前(PN.せりざわ悠)はなく、
「やっぱりだめかー。そもそも間に合ったかあやしいしなー」
と諦めていたのですが、昨日公開されたnoteを見てびっくり。
「最終候補一歩手前」に私の作品が載っていたのです。
一番上にあったので画面をスライドしかけて「ん?んん?」と戻りました。
これを見た瞬間のじわーっとこみ上げてくる喜び、分かるでしょうか。
もう本当にダメだと思ってたんですよ。
締切30分前に投稿しようとしたらエラーが出てしまい、
「なんで!なんでなの!?」
と半狂乱になりながら何度も入力しました。
時計を見るのが怖くてひたすらキーボードを叩き続け、
「お願いっっ!!」
と絶叫しながらの「送信」。
最後に完了画面が出たときは力が抜けて倒れそうでした。これぞまさにホラー。
ここまで読んで「なんだ内容の話じゃないんかい」と思われた方、すみません。
そうです。無事に間に合った嬉しさを噛みしめているのです。
でもそれだけじゃないですよ。
以前も触れましたが私ホラーが苦手で、書くのも得意ではありません。
なので今回のホラー小説に一定の評価をされたことは大きな自信にもつながりました。
講評はこちらを見ていただくとして、お褒めいただいた祭りの描写を一部載せておきますね。
なお講評の内容自体は的確すぎてぐぅの音も出ません。さすがジャンプ。
「月と皮」冒頭公開
【序章】
祈りはむなしく夕暮れ前から雨が降りだした。夏の暑さで干からびたアスファルトに叩きつける雨粒は激しく衰えを知らない。このまましばらく降り続きそうな勢いだった。
「残念だったな拓巳(たくみ)。夏祭りは中止だ。だから予報は当たると云ったのに」
軒下に吊るしたテルテル坊主をにらんでいた少年の頭を、後ろからやってきた兄が乱暴に撫でた。からかうような口ぶりに反して髪を撫でる手は優しい。その優しさが「あきらめろ」の裏返しのような気がして、拓巳はますます腹を立てた。
「兄ちゃんは悔しくないの? ぼくたち七年祭のためにはるばる東京から来たんだよ」
体を反転させ、居間の座布団の上で本を開く二つ上の兄に声をかける。分厚い人体図鑑のページをめくっていた兄の晶(あきら)は顔を上げずに笑った。
「まだ七歳のくせにどこで『遥々』なんて言葉覚えてきたんだ? 東京からたったの二時間程度は遥々なんて云わない。それに旅行の目的は夏祭りじゃなくて避暑だ」
拓巳たちはこの土地の人間ではなく旅行者だ。両親が新婚旅行で訪れた『月黙亭(つきしまてい)』の宿を気に入り、毎年夏になると家族旅行を兼ねてこの宿にやって来ているのだ。女将たちともすっかり顔なじみになっている。
「だからって、このままお部屋でじっと雨垂れを数えているなんて我慢できないよ」
十畳の和室には兄弟ふたりきりだ。一緒に来た両親は別館で大人の祭りを愉しんでいる。女将の計らいで、地酒や刺身がふんだんに振る舞われているのだが、いくらジュースをたくさん飲めるといっても酒臭い会場にそう長くはいられないので、子どもたちは一足先に部屋に戻ってきていた。
床の間に飾られたヒマワリは下を向いている。拓巳も同じようにうつむいて晶の膝にごろりと頭を乗せた。
「香子(きょうこ)サンは?」
月島 香子は宿のひとり娘で晶と同い年の九歳だ。
彼女のことが話題に上がると晶は途端に不機嫌になる。態度には出さないがいくぶん声が低くなるのだ。幼い拓巳にとってそれは一面が土で覆われた公園で落とし穴を探すような作業で、つい慎重になる。
「さぁ? 朝早くから夏祭りの準備に出掛けたからな。中止が決まるまでは会場の神社にいるんじゃないか?」
どうやら今回は落とし穴を逃れたらしい。規則的に上下する晶の睫毛を眺めていた拓巳は満足そうに頷いて上体を起こした。ポケットに隠していた硬貨を掴んで拳を上げる。
「じゃあ行こうよ。中止になるまでは夜店がやっているんだろ?」
「――莫迦」
嘆息した晶はいまにも部屋を飛び出しそうな拓巳を捕まえて腕の中に引っ張りこんだ。
「ぬかるみに足をとられて転ぶのは誰だ? 小遣いをばらまいて泣くのは誰だ? 泥だらけになったおまえを背負って会場へ向かうのは誰だ? どこの祭りに行っても同じようなことを繰り返していることにいい加減気づけよ。もう懲り懲りだ」
吐息がかかるほど近くで呆れ顔を見させられると、さすがの拓巳も申し訳ない気持ちになる。祭りに行きたいのは本当だが兄に迷惑をかけたくないという気持ちも本当だ。
「分かった……」
おとなしく聞き入れてうなだれる。しかし晶も鬼ではない。拓巳がこの狐塚の夏祭りを指折り数えているのを知っている。
七年に一度、土地の守り神である狐を奉るため神社一帯に蝋燭が灯される。その光は狐火のように怪しげで、神社のある稲荷山を一晩中明るく照らすのだ。執り行われる祭事の内容は一般的な祭りとも大差ないが、狐塚特有の湿った空気の中で見る灯りは雰囲気がまるで違う。とは云っても、幼い拓巳の目的は祭りそのものではなく目先の夜店だ。
「香子に連絡して、開いている夜店で買ってきてくれと頼むよ。何が欲しい?」
拓巳はパッと顔を輝かせた。
「わたあめ。それから、くれーぷ。あとね、たこ焼きと、焼きそばと」
「莫迦。いいか、おまえの小遣いは五百円。夜店で買えるものはひとつだけだ。自分が本当に欲しいもの、よく考えろよ。あとで後悔して泣いても許さないからな」
おどしつけるように云い含める。
「……ひとつだけだね」
正しく理解したのかどうか、拓巳はじっと晶の眼を見つめた。
「なんだ? オレの顔に何かあるのか?」
「ううん、なんでもない。ぼくわたあめが食べたい。ふわふわして、やわらかくて、まっしろで好きだから」
たこ焼きや焼きそばはファミレスでも食べられるがわたあめはそうはいかない。特に祭りで食べるわたあめは格別に美味しい。
「分かった、頼んでみる。おまえはここにいろ、動くなよ」
「トイレもだめ?」
「畳を汚したら承知しないからな」
念押しするように告げると母の携帯電話を握りしめて部屋を出て行った。拓巳はひとり寒々しい室内に残される。窓が叩く雨音がひときわ大きくなった気がして、慌てて入り口側に移動した。
数分待ったが晶は戻ってこない。ウトウトしはじめたところへ誰かの声が聞こえた。
『夏祭りに行こう』
トントン、窓硝子が揺れる。しかし窓の外は一面の霧。庭先の燈籠すら見えない。
拓巳は無言のまま体を強張らせた。
『迎えに来たよ。一緒に行こう』
トントントン。ふたたび窓硝子が音を立てる。霧の中に縞柄の浴衣が揺らめいた。
「夏祭りは中止だよ。誰も行かないよ」
半べそになって訴えても霧の中に佇む者は立ち去らない。むしろ近づいてきている。
『そんなことはないさ。ほら、聞こえるだろう?』
どこからともなく笛の音が響いた。祭囃子だ。楽しげな音色に人々の笑い声も混ざり合って、目を開けていなければここが部屋だということを忘れそうだった。
「――兄ちゃん、兄ちゃんッ」
爪先を蹴って廊下へ飛び出したが電話をかけているはずの兄の姿がない。静まり返った薄暗い廊下では消火器の紅いランプだけが不気味に光っている。
『お兄さんは先に行ってしまったよ。面倒なきみを置いて、今頃は夜店の前さ』
声が近い。縞柄の浴衣を着た少年が窓枠に腰を下ろしていた。背格好は兄と同じくらいだが顔に狐の面を当てているため表情は分からない。開け放たれた窓から冷たい夜霧が侵入してくるが雨の気配は遠のいていた。少年の浴衣も濡れていない。
『見えるかい、もう祭り会場は人と屋台でいっぱいだよ』
遠くに見える稲荷山には赤い光が尾を引いている。祭りの灯りだ。
その灯りを目にした途端、拓巳の中から少年への恐怖がかき消した。祭りは中止にならなかった。それなら一刻も早く兄のところに行かないと。そんな意識に支配される。
『さ、行こうか』
拓巳は大急ぎで蜻蛉柄の浴衣に着替えると青いサンダルを履いて外に出た。降り続いた雨は草木やアスファルトがためこんだ夏の熱気を吸い取って、霧と異様な湿気に換えている。それはまるで大きなわたあめのようだった。
見慣れた街並みは夕霧に包まれ、行き交う人影は小舟のように浮かんでは沈む。通りすぎる人や建物が次々と『わたあめ』に包まれて消えていくのを空恐ろしい気持ちで見つめていた。いつか自分も食べられてしまうんじゃないか、想像すると震えが止まらない。
『大丈夫だよ』
拓巳の心を察したように少年が手を握ってくれた。あたたかい手だ。拓巳は安心する。
風が強くなり、さぁっと霧が晴れた。遮るもののない群青色の夜空が姿を現す。小走りに横切る雲の合間からはきらきらと輝く満月が垣間見えた。
「みてお月さまだよ。どうしてお月さまはあんなにきれいなのかな?」
兄に尋ねるときのように疑問をそのまま口にした。
『月が星を殺しているからだよ』
大股で歩いていた少年はなんの抑揚もない声で答えた。
『月はぼくたちが見えないところで星を殺し、星がまとっている金色の皮を剥いでいるんだ。そして我が物顔でそれを着て空に浮かぶ。だから月はあんなに綺麗なんだ。皮を全部剥がしたら、クレーターで凸凹に歪んだ醜い球体が残るだけさ。おれもそうなんだ』
拓巳は改めて少年の顔を眺めた。微妙に色合いの異なる朱が丹念に入れられた狐面。三日月形に刳り貫かれた穴の向こうにある目玉が不気味に輝いている。
「どうしてお顔を隠しているの? 悪いことでもするの?」
最近見たテレビの影響で顔を隠すのは悪いことをするからだと思い込んでいた。あまりの正直さに少年も肩を揺らして笑う。
『悪いことをするんだよ。おれが付けている面は他人の〈皮〉なんだ』
「……かわ?」
先ほど云っていた星の皮のことだろうか、と首をかしげる。
『蛻皮(もぬけがわ)……と云っても分からないか。セミや蛇の抜け殻、人間で云えば毎日のように脱ぎ着する衣服だと思えばいい。肉から剥ぎ取って特殊な薬液を塗り、丁寧になめしてから乾かすと、こんなふうに一見ただの面になるんだ。持ち主の記憶がすこしだけ残っているから、たまにぎょろぎょろと目玉を動かすけどね』
変身グッズみたいなものだろうか、と理解した。
いつの間にか神社の敷地内に入ったらしい。草履ごしに砂利の凹凸が感じられる。そのくせ周囲は暗幕に覆われたように暗く、月も星も見えない。唐突に少年が立ち止まった。
「きみには欲しいものがある?」
「わたあめ」
『わたあめね、うん、それでもいいんだけどさ。いまきみの手の中には五百円玉があるだろう。それでひとつだけ、何でも買えるとしたらどうする?』
何が云いたいのか、拓巳には分からない。
『正直に云うよ。おれはきみの皮が欲しい。いまだって涎が垂れそうなのを必死にこらえているんだ』
目の前の少年は自分を狙っている。不思議と恐怖は感じなかった。こんなにあたたかい手の主が自分に危害を加えるとは思えなかったのだ。
『おれだけが貰ったら不公平だから、先にきみの願いを叶えてあげたいんだよ』
妙に律儀な、変な少年だ。拓巳もなんとなく分かってきた。この少年は『人間』ではない。あたたかな手と規則的な呼吸を繰り返す体を持っているが、人間とはすこし違う。
拓巳は手をほどいて少年の顔を覗き込んだ。
「じゃあ、お顔を見せて。そうしたら教えてあげる」
『……いいよ、みてて』
少年自ら面に手をかける。カチリ、と音がしてゆっくりと狐面が動いた。拓巳の胸はドキドキと鳴る。
『なんてね』
少年の顔を見る間もなく、外れた狐面はそのまま裏返しにされて拓巳の顔に近づいてきた。鈍色の裏面が間近に迫る。ひやりと冷たいものが肌に当たったと思った瞬間、向こう側からぎゅっと《吸われた》。
「助けて」と叫んだつもりだったが声にならない。狐面は執拗だ。離れない、目が開かない、息ができない。爪先が浮くのが分かった。それでも狐面は夢中で拓巳を吸う。目や鼻の形をひとつずつ埋めながら形をとり、まるで精巧な仮面を作っているようだ。
『だから云ったのに。悪いことをするって』
握りしめていた五百円玉がすべり落ちて転がっていく。追いかける足音はない。